「偶然を捉えて幸運に導く力」をセレンディピティ(serendipity)という。
辞書にはものをうまく発見する能力、堀出し上手とある。
英国の作家ホーレス・ウォルポール(1717~97)の造語。ウォルポールが「セレンディップの3王子」の物語を読んで感銘し、「偶然の大発見をセレンディピティということにしよう」と友人たちに呼びかけたというもの。
歴史上で有名なのは、ニュートンの万有引力の発見、フレミングによるペニシリンの発見、3M社のポストイットなどがあげられる。
ポストイットは日頃からお世話になっているが、強力な接着剤を作ろうとして、却って弱い接着剤を開発してしまったケース。
何か用途があるはずと考えてもなかなか見つからなかった。賛美歌のしおりが落ちた経験から生まれたという。
セレンディピティを能力だとするとどのようにすればセレンディピティは高まるのであろうか?
「成功者の絶対法則 セレンディピティ」にはセレンディピティのケースとその要因が分析されている。
著者はセレンディピティを具体化する困難さを説いている。
発見するよりは具体化する方が難しいのだ。
「見えざる顧客を見つけたものだけが生き残る。」
「素人発想を玄人実行する」
偶然の発見というが、データの収集と蓄積、常に考え続けたからこそ、「偶然」に発見する確率が高まっているのだろう。
知恵とは情報の組み合わせ。組み合わせをするための情報量が第一。
組み合わせの多様性は既存の情報に新たな情報をシャワーのようにぶつけることによって生まれる。アイデアはその問題自体とは関係のないことを考えている時に思いつくことが多い。
突然変異のようなものなのだ。
ある情報に別の情報が加わると全く別のものに見えてくることがある。
関係性のない問題を関係付けることができる。情報の組み合わせが問題なのだ。
ホーレス・ウォルポールが読んでセレンディピティを造語した寓話。
セレンディップとはスリランカの古名。
その3人の王子が、王様から「竜退治の秘法」の書いた巻物を探すよう指示され、その巻物を探す物語。
結局巻物は見つからないのだが、3人の王子は旅の途中でお妃を見つけ、無事にセレンディップに帰ってくる。
竜は金の鳥が退治してくれ、3人とも幸せな生涯を送ったという。
目的であった巻物を探す過程でお后を探しあてたのだ。
ホーレス・ウォルポールを感動させたのは何か?
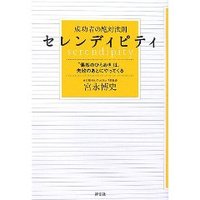
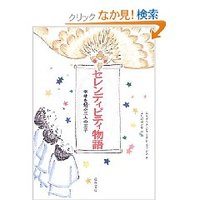 「
「
コメント