ネットのあちら側とこちら側
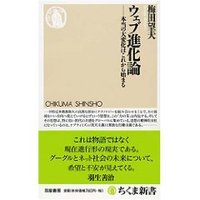
以前から言われていたネットワークコンピューティングが昨今の「チープ革命」によって実現した。
”こちら側”のPCにソフト・情報を置いておくのではなく、”あちら側”、たとえばgoogleのストレージに置いておけば、常にどこからでもその情報にアクセスでき、検索も1発で可能だ。
会社のストレージ、PCのHDや個人のPCなどに情報が分散していると検索も同期もストレスの原因となる。”あちら側”に置いておけるものであれば非常に便利だ。
ただし、信用できるのであれば!
ユーザーが情報を”あちら側”に置くことにより、”あちら側”の運営者は「神の視点(全体を俯瞰する位置)からの世界理解」をすることができる。
特定のユーザーが何を検索(探して)しているのかを知ることは、そのユーザーのニーズを理解することである。
また、amazon.comでどのような書籍や商品を検索し、購入しているのか?
それは特定のユーザーが、何を考えているのか、どのような思考プロセスを辿っているのかを理解することができるかも知れない。
gmailの文章の内容をシステムで分析すると...
1件1回だけの情報ではなく、多数の様々な情報を継続的・多角的に分析できるとすると...
その上、本人だけでなく、家族や仕事の関係者の情報がリンクさせて理解できるようになると...
ユーザーの立場から考えると、安価(ただ)で様々なサービスを使用する代償に、個人の情報を開示する必要があるわけ。
しかし、それが何か問題となるのか?
個人の情報の開示が利便性につながるメリットは大きい。
自分自身で気付かないニーズに対してアドバイスを受けることができるから。
Webである商品を購入すると、あれはどうか、これはどうか?とおすすめ商品が出てくるが、意外と便利だと思うときがある。
正面にしつこいセールスマンがいる訳ではない。
買うか買わないかは自分で冷静に判断できる。
消費者とのリレーションシップを取るためには消費者の固有の情報の集積が不可欠だが、Web2.0の仕組みは消費者自身がすすんで”あちら側”の運営者に自己開示をするように仕向けている。
ロングテールのテールの部分でも販売サイドは充分にコストに見合う商売ができるようになってきた。
また、顧客参加型の仕組みは顧客が意識的に参加しているか否かはさておいて広い意味ではオープンソースと考えてもよいのではないか。
しかしながら、消費者も提供する情報にはある程度選別が必要だろう。見られていることがどのように影響が出てくるか未知数だ。
社会保険庁において職員が有名人の年金加入記録にアクセスして暴露したようなことがないとも限らない。個人情報を社外に販売する事件も後を絶たない。自己責任の原則はWebのような秩序のない世界には一層厳しく存在すると考えていた方がよい。
本当に世界はフラット化してきた。
コメント