「パラノイアだけが生き残る」が有名となったが、”戦略的転換点”の把握と対応に関する書。
"Sooner or later,something fundamental in your business world will change."
1980年代初めに主力のメモリー事業を日本社に追い上げられて、苦境に追い込まれた。その解決策として、主力のメモリー事業から撤退し、マイクロプロセッサー(MPU)に事業を集中して今のインテルを築きあげた話
1985年の決断の元になった会話が生々しい。
グローブがムーアに対して「もし、我々が追い出されて、新しいCEOが来たら、その男はどんな策を取ると思うかい?」と問うたのに対してムーアが「メモリー事業を廃止するだろう」と答えた。グローブは「それであれば、われわれでやろう!」
しかし、386というCPUの開発がほぼ終わっていたということも決断できた要素のひとつであることを認めている。
<垂直統合から水平分業へ>
私が気になったのは戦略的転換点の話より水平分業の部分だ。
80年代半ばにコンピュータ業界が垂直統合から水平分業になることを見通しているのはさすが
すなわち強力な部品(MPU、OS、HD、メモリ)があれば商売になるが、組み立てているだけでは儲けが出ないということだ。
IBMはずいぶん昔にPC事業を中国のレノボに売却している。日本のメーカーの製品も残念ながらハードに差があるとは思えない。
消費者が欲しているのは購入後のサポートの手厚さなのだ。
グローブは水平分業の新たなルールとして下記を挙げている。
<1>無闇に差別化しない。互換性のない「よいパソコン」は技術的に矛盾している。
<2>時間的な優位性を保つ
<3>市場に受け入れられる価格
水平分業はフラット化した世界においてこれからあらゆる産業に広まっていくであろう。
基本的な「部品」あるいは「取引」の仕組みを可能な限り標準化する結果、消費者の利便性を高めて、かつコストダウンを狙うのである。
水平分業はPCのOSやアプリケーション、Webのブラウザなどの例がわかりやすい。最近経験したのは、交通機関の切符の購入だ。
SUICAとPASMOは首都圏で共用できて便利だが、名古屋圏に来ると、JR東海は2つとも使えるものの、名鉄では使えない。
競合する路線では名鉄に不利に働くだろう。名鉄に乗車するためには自動券売機の前にならんで、上の料金表で目的の駅を探し、料金を確認して、その料金を自動販売機に入れて、ボタンを押す作業をする必要がある。
切符を買うという作業を乗客に強いていることになる。
老人が自分の前にならんでいると大変だ!
昔は当たり前のことだったが、今は違う。切符(紙)は買わないというのが常識になったのだ。
一方、意味のない差別化は意図的に行われる場合が少なくない。その目的は強い競合との商品・サービスの違いをあえて消費者にわかりにくくして現状を維持することを狙う場合だ。ほとんど意味のない機能を付加して価格を高く設定したりする。
携帯電話なども多機能であるが、カメラなど全部の消費者が必要としていうとは思えない。
しかし、そのような抵抗は長続きしないだろう。
大差ない差別化は社会全体のノイズとみなされて、消費者から無視される可能性がある。
簡単にいうと面倒だからやめた。ということだ。
セブン・イレブンのNANACOも囲い込みを狙って独自カード化しているが、他のカードは使わせない。
了見が狭い。これも両刃の剣だ。マイラーは当然敬遠するだろうが、さらに、標準化を拒む姿勢に消費者が反発するのではないか?
ソニーも音楽のデジタル化で独自ソフトを流通させようとして失敗している。
<社会の大転換点>
インテルは1985年を自社の戦略的転換点と認識して生き残った。日本社の追い上げをノイズではなくシグナルと受け止めたのだ。
自動車業界はどうだろうか?GM,クライスラー、フォード...
グローブは認めている。戦略的な転換点を認めて乗り越えていくのは、とてもウエットできわめて感情的な問題であると。経営者は皆過去のやり方の成功者なのだ。
だからこそ、困難な決断。
カルロス・ゴーンが日産の社長になったのは以前の経営者がわかっていたけれどもできなかったから彼を呼んだといわれている。わかっていたけどできなかったのだ。しがらみのないゴーンだからこそできた。
現在の経済危機はアメリカの金融が原因とされているが、実はテクノロジーの発達と情報の均質化などにより、消費と産業構造が大きな転換点を迎えていると見るべきだと思う。
であるから、どこもかしこも、過去を否定して乗り越えていかない限り、問題は解決しない。
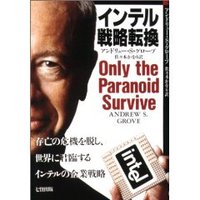
コメント