invention は science というより art である
Juice:The Creative Fuel That Drives World-Class Inventors
by Evan I. Schwarz
本書の読了はまさに始まりの終わりにすぎなかった。のぞき込んだ針が開けたほどの穴の奥があまりにも広かった。すぐに登場人物一人一人の深掘りをしたくなってきた。
本書はそんな発明家たちのもつ思考と性癖を発明家に必要な要素としていくつかのカテゴリーに分けて分析している。それに至る事実の検証と論理構成が見事。
エジソン、ベル、ライト兄弟くらいは私でもある程度の知識があったが、ノリス、ウォーカー、フッドなど多数の登場人物の発明したモノに関してはなんとなく名前くらいは聞いたことがある程度で、具体的な内容や発明者に関してはほとんど無知であることが露呈した。一方、GMの前社長がワゴナーだとか、神奈川県知事の名前が松沢だとかは知っているのにもかかわらず、現在の生活に大きな影響を及ぼした発明者に対して一般的に大きな光が当たっていなかったことも事実である。先日、日本人で3名の科学者がノーベル賞を受賞したが、失礼ながら受賞されて初めてそのような発明と発明家がいたことを知った次第でもある。
発明が商品・サービス化されるまでには時間がかかる。すでに手にしているものに対して人はありがたみを感じることは少ないということか。それは必要性が先が、発明が先かという議論にも結びつく。蓄音機も電球も映画もLEDも消費者が開発を熱望していたわけではない。発明があってニーズがそれについてきたものが大半であった。市場調査、あるいは世論調査などというものがどれだけ意味があるか疑問だ。知らないものは欲しがれない。
先のノーベル賞の受賞者も早く受賞されてよかった。へたをすると、墓場で受賞ということに(死者に対して受賞があるか否か知らないが)なりかねない。その意味ではartのように見える。しかし、エジソンがゴッホやゴーギャンと同じかと言われるとそれは全く違う。発明は現実化して初めて意味がある。だからこそ、開発競争は常に激烈だ。
発明家の可能性を創出しようとする原動力についてユングのことばを引用している。
私はこの言葉に救われた気がした。
「独創性に満ちた心は好きなものと戯れる。」
「新しいものを創造するのは知性ではなく、内的必然からはたらく遊びの本能である。」
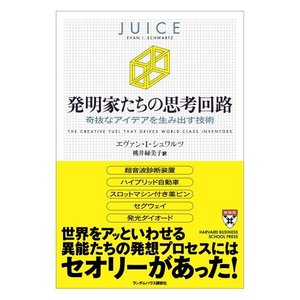
コメント