Cloud :雲、雲のように大きい
メインフレームへの回帰
↓
クライアント・サーバー(分散処理)
↓
Webコンピューティング(集中処理)
↓
クラウドコンピューティング(集中処理)
Service not software or hardware
データ処理量と処理能力の相対性によって演算する場所が、集中→分散→集中と変遷をたどってきた。
Google(goog),Amazon.com(amzn),Salesforce.com(crm),IBM(ibm)はクラウドコンピューティングの巨人といわれている。
ユーザーは手元にソフトウェア、サーバーを保有しなくてもよくなりつつある。すべてレンタルで使用量に応じた費用を支払えばよいのだ。よい例はこのblogだ!ソフトもHDも手元にはない。全部Cloud側にある。それを借りている。コストは非常に低廉。このblogは有料だが、大半は無料だ。PCは端なる「窓」であり、ブラウザがあるだけ。PCが計算する処理はほとんどなくなる。思い起こしてみれば、メインフレームの時代は「窓」のことを「端末」と言っていたものだ。またその時代に帰ってきた。すべてクラウドの向こう側で処理して演算の結果だけを「窓」に返してくれる。しかも低コストで。
その影響は、またしても中抜きという効果をもたらす。高度なMPUを搭載したPCは不要となり、HDも不要、PC用のソフトウエアも不要、販売店も不要、パソコン教室も不要。残るのは集中処理を行うクラウド側のCPUとHDと通信回線となる。
ただ、一つ問題なのは信頼性。本当に大事なものは自身で管理・バックアップしておく必要があるだろう。しかし、それは程度の問題で、あまりにも保守的に考えると、大きくコストに跳ね返ってくる。
Salesforce.comが成功したように、多くのユーザーが個別にソフトウェアを開発する必要は少ない。ユーザーが抱えている課題はさほど変わりなく、差異はほとんど嗜好の世界。アウトソーシングできるものは可能な限りアウトソーシングして自己のコア業務に資源を集中しないと生き残れない。
何をコア業務とし、何をアウトソーシング可能とするかの判断は、自身の事業の定義の問題。
そして、様々なアプリケーションを出来合のソフトウェアで処理しようとすると、競合との差異は徐々に小さなものであることが帰納的に明確になっていくだろう。その結果は、情報処理業者の大型化だけではなく、あらゆる産業のおおくくり化を推し進めることになる。差異の小さい企業群が生き残る理由が乏しくなってくる。
一方、ニッチで個性的な事業は立ち上げから保守に至るまでコスト面で非常に楽になるために、創業しやすくなると思われる。まさに、第四の波が、New Typeを出現させる。しかし、Old Typeはなくなるわけではない。非常に大きくおおくくり化されてコモデティとして生き残る。単価は激減しているが、競合が少ない中において集積するとそこには大きな収益が。
クラウドコンピューティングの巨人たちは買いであろうか?現在の株価は停滞しているように見える。市場が気づいていないのか、すでに成長を織り込み済みの価格であるのか。
この問題における選択は巨人の株式を購入することではない。集中処理できるようになった自身の仕事(フラット化したとも言える)のあり方をどうするか。さらに集中処理できるようになった環境に適したどのような事業領域を選択し、どのタイミングで他社に先駆けて展開することである。
<クラウドコンピューティングの3つの形態>
Saas:Software as a Service
Haas:Hardware as a Service
Paas:Platform as a Service
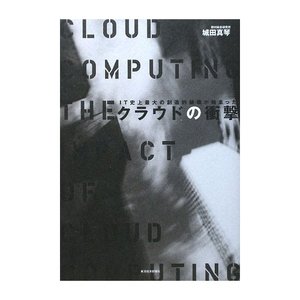
コメント