自分の知性への不信感
by Nassim Nicholas Taleb
「吹き飛ぶトレーダーに特徴的なのは、自分は世界がどのようになっているのかとてもよく知っているので、ひどい目にあう可能性はないと思い込んでいることだ。彼らがリスクをとれるのは彼らが勇敢だからではなくて、全然わかっていないからだ。」
ブラック・スワンの前作
読む順番が逆になったが、こちらの方がタレブの考えがわかりやすい。
統計・確率に対する見方の革命。自分の予測能力に対する過信の戒め。さらには、ランダム性の受け入れへの心構え。ランダム性を前提とした生き方の主張。
そう言われてみると、確かに、世の中の情報は問題が発生した後に後知恵バイアスがかかったものばかりだ。
下記のような大きなランダムな出来事は誰も予測できなかった。しかし、後知恵バイアスはその原因を後知恵でかつ限られた要素に帰して単純化してしまう。帰納法の罠である。その経験はエルゴード性により、その後の予測には役に立たない。
1987年のブラックマンデー
1990年の日本のバブル崩壊
1994年の債券市場の暴落
1998年のロシア危機
2001年9月11日
2008年のリーマンショック
タレブの指摘はピーター・バーンスタインも同様に「リスク」においてライプニッツがベルヌーイに宛てた書簡として紹介している。「「自然は事象の原点へと回帰するパターンを確立したが、それも大半の部分についてでしかない。」このような仮定条件がなければ、万物はすべて予測可能であり、すべての事象は過去の事象と同じになり、何らの変化も生じなくなる。」
多数のおもしろい例話のいくつか
クロイソス王に今の栄華が将来に向かって続く保証はないと言いのけたソロンの戒め。
タイプライターの前の無限大匹のサルは「イーリアス」を書き上げる。
サルの数が多ければ「イーリアス」は書ける。問題は母数なのだ。書けたという結果から蓋然性を導き出すのは間違っている。
ロシアンルーレット。リボルバーの弾倉は6発だが、日常を暮らしていると6発が何千発にもなる。そうなると、いつの間にか弾倉に弾丸が装填されているのを忘れてしまう。そして長い時間の経過の中でいつか自分の頭を打ち抜いてしまう。
後知恵バイアス。過去を予測するのがとてもうまい連中が自分は将来を予測するのもうまいのだと勘違いして、自分の能力に自信をもってしまうのだ。
ある結果だけで(エルゴード性を無視して)将来をわかったような気になってはいけない。その結果以外の可能性(違った歴史)を想定してみる。結果ではない、経過が大事なのだ。
本書からストレートに引き出される行動はない。ただ、その通りであると認識して生きるという選択をするか否かである。しかも、ランダム性は理性で対処できるものではない。どうしようもない感情をごまかすリスクマネジメントの最終形は哲学か、はたまた宗教か。
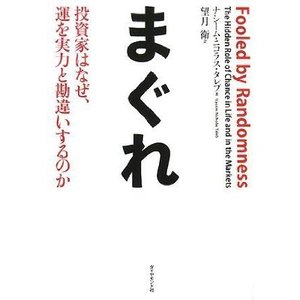
コメント