選択における現在と将来、そのウエイト
 最近は蝉の鳴き声で目が覚める。朝5時くらいから蝉が鳴き始めるのだ。向かいの家の庭木に蝉が舞っており、かなりの数が集結していると思われる。蝉の鳴き声はただでさえ低からぬ気温を押し上げるような気がするとして嫌う方もいるようだが、私は好きだ。
最近は蝉の鳴き声で目が覚める。朝5時くらいから蝉が鳴き始めるのだ。向かいの家の庭木に蝉が舞っており、かなりの数が集結していると思われる。蝉の鳴き声はただでさえ低からぬ気温を押し上げるような気がするとして嫌う方もいるようだが、私は好きだ。
子供のころ、ヒグラシが鳴き始めるともう夏休みも終わりだと寂しく思ったのを覚えている。暑くて憎らしかった真っ赤な太陽さえもそのままでいて欲しい思う晩夏。短い夏の間にも季節感がある。太陽の季節というように生命の時なのだ。
昨年まで住んでいた札幌では蝉の声を聞くことはなかった。もっとも、蚊もゴキブリもいないところだから当然。その点で北国に虫の話は少ない。
夜の虫のコンサートもいい。人間の楽器では出せない生命の和音。彼らは生きるために歌っているのだ
そんな虫も擬人化して選択の材料としてもてはやされる。イソップはその達人だ。イソップは南の国ギリシャの生まれなのだ。虫にはことかかない環境にあったことになる。
私も「選択」の例話としてイソップ寓話の「蝉と蟻」を使うことがある。一般的には日本では「蝉と蟻」ではなく、「蟻とキリギリス」となっている。その話は次回にする。「蟻とキリギリス」の話はいろいろとバリエーションが多彩で、かつその結果選択も変わってくるのでおもしろいのだ。
<蟻とキリギリス 基本形>
「夏の間蟻は食べ物のない冬に備えて一生懸命食べ物を集めて巣穴に運び込んでいました。一方、キリギリスは夏の間歌って踊って暮らしていました。冬が来て食べ物のなくなったキリギリスは蟻に食べ物を分けてもらおうと蟻の家に行きました。」
「蟻はキリギリスに夏の間歌っていたのであるから、冬の間は外で踊っていないさいと言って結局食べ物を分けてあげませんでした。」
食料のない冬に(将来)備えて夏(現在)に備えをしておきなさいというメッセージになる。将来のために現在を犠牲にするという選択。この基本形は老後の生活資金への備えなどに効果的だ。
これが逆だとモラルハザードになる。こんな感じ
「かわそうに、寒いでしょう。中に入って一緒にご飯を食べましょう!」
自分は備えておかなくても、誰かが助けてくれると思ったら、だれが、一生懸命働こうとするだろうか。最近の選挙を巡るバラマキの公約はキリギリスを蟻が支える図式といえる。蟻がいつまでも稼いでくれればよいが
<蟻とキリギリス 発展形>
「冬が来て食べ物のなくなったキリギリスは蟻を対象にコンサートを開き、入場料として食料を受け取りました。」これは竹内靖雄氏の「イソップ寓話の経済倫理学」に紹介されていた。夏の間の歌を仕込みと考えてサービスの提供で冬を乗り越えようとする考え方。これは視点の問題もある。当然芸術家は食べ物を集めるのが仕事ではないから
<蟻とキリギリス 番外編>
「冬が来て食べ物のなくなったキリギリスは蟻に食べ物を分けてもらおうと蟻の家に行きました。蟻の家の戸たたいても誰もでてこないので、中に入ってみると蟻が過労で死んでました。キリギリスは蟻がため込んだ食料で春までゆうゆうと暮らしました。」将来に備えるあまりに体を壊してしまっては元も子もない。将来に備えようとするあまり、将来を失ってしまったケース。笑えない話だ。実はこれに似たケースは決して少なくない。
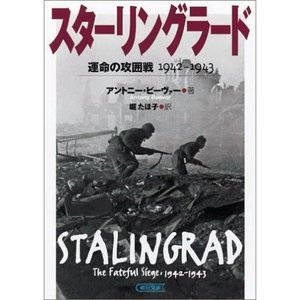 これに似た話が第二次大戦中の有名なスターリングラードのドイツ軍であったというのだ。ご存じのとおり、1942年の11月にドイツ第6軍はロシア軍によってスターリングラードに包囲された。その後補給不足のために多くの兵士が亡くなった。が、包囲される前から補給責任者が冬に備えて食料の配給を減らしていたというのだ。(包囲はされないという前提で)しかし、すでに補給を減らされて弱っていた兵士に包囲による食料不足が追い打ちを掛けて突然死を促進したというのだ。(アントニー・ヒーヴァー「スターリングラード」)
これに似た話が第二次大戦中の有名なスターリングラードのドイツ軍であったというのだ。ご存じのとおり、1942年の11月にドイツ第6軍はロシア軍によってスターリングラードに包囲された。その後補給不足のために多くの兵士が亡くなった。が、包囲される前から補給責任者が冬に備えて食料の配給を減らしていたというのだ。(包囲はされないという前提で)しかし、すでに補給を減らされて弱っていた兵士に包囲による食料不足が追い打ちを掛けて突然死を促進したというのだ。(アントニー・ヒーヴァー「スターリングラード」)
現在と将来へのウエイト配分の選択。将来のためにある程度現在を犠牲にすることが必要なのは明らか。問題は将来を見越してどの程度現在を犠牲にするかという選択なのだ。
(つづく)
コメント