そう言われればそうかもしれない不確実性
「ブラック・スワンー不確実性とリスクの本質」
陥りがちな思い込みをチェックするガイド
七面鳥は毎日親切な人間からエサをもらう。それが1000日続き、この人が一番親切な人であると信じている。そして、これ以降もずっとエサをもらえるのだと…... しかし、1001日目、感謝祭の前日にその親切な人から首をひねられる。経験から将来を推論する帰納法のリスク。経験にはよい経験と悪い経験がある。さらにそのデータが仕組まれたものであったら。七面鳥のケースはまさに仕組まれた罠だったのである。七面鳥は実はカモだったということになる。
カモにならないようにするには?
目に見える一部のデータから目に見えていない部分にまで一般化してしまおうとする人間の習性と安易に他人の予想を鵜呑みにする危険。
「黒鳥がいる可能性があると示す証拠がない」を「黒鳥がいるという可能性をないと示す証拠がある」を混同してしまう。結果として「黒鳥はいないと示す証拠がある」と理解してしまう。そうである証拠をいくら積み上げても見えていない黒鳥はその裏付けの領域には入っていない。「トンネル化」:例外を考慮しない習性。そこで、むしろ、反証を上げて内容を実証していくしかないとしてカール・ポパーの半懐疑主義を取り上げている。
さらに、霊長類ヒト科はパターンを好み、要約、単純化が好き。因果関係を求めたがる(プラトン性)。連なった事実を見ると、一連の事実に論理的な繋がりを無理矢理当てはめてしまう。ガウス曲線で、中心値で物事を判断してしまう。このようにすれば、事実を簡単に覚えられるし、わかりやすくなる。しかし、危険なのはこの性質のせいで「わかった気になる」時だ。
「情報がランダムであるほど次元は高くなり、要約するのが難しくなる。要約すればするほど、当てはめる法則は強くなり、でたらめでなくなる。そんな仕組みが一方で私たちに単純化を行わせ、もう一方で私たちに世界が実際よりもたまたまではないと思い込ませる。」
演繹的に考えているつもりで実は帰納的な判断をする場合が一番危ない。講釈の誤りを防ぐためには、物語より実験を、歴史より経験を、理論より実証を重んじることと主張する。
ご指摘は至極ごもっともだが、その解決策として下記のようにまとめている。
「ありえないことが起こる危険にさらされるのは、黒い白鳥に自分を振り回されるのを許してしまったときだけだ。自分のすることなら、いつだって自分の思いのままにできる。だから、それを自分の目指すものにするのである。」
「ただ生きているだけでもものすごく運がいいのを私たちはすぐに忘れてしまう。それ自体がとてもまれな事象であり、ものすごく小さな確率でたまたま起こったことなのだ。…………あなた自身が黒い白鳥なのだ。」
哲学的であるが、予想は期待の裏返し。1000日間カモをだまそうとする輩がちまたにあふれている。七面鳥になるか否かは自分自身が黒い白鳥になることだ。いすれにしても人生はままならない。その前提で生きた方がいいよということであると理解した。究極のリスクマネジメントは自分の人生への期待値の設定かもしれない。成功と失敗を何で測るか、その選択が自分の人生を左右する。
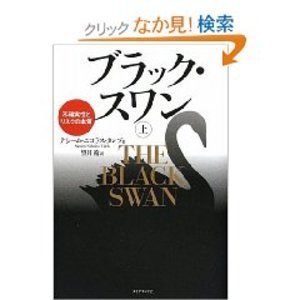
コメント