CIVILIZATIONに学ぶ知識の力
持てるものと持たざるものの歴史
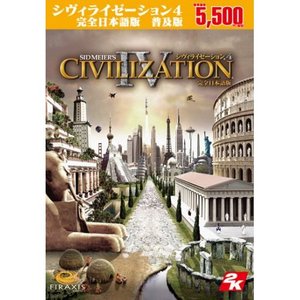 数年前にCIVILIZATIONというPCのゲームにはまっていた。これは人類の誕生からギリシャ、ローマ時代を経て中世、ルネサンス、大航海時代、現代、宇宙の時代へと自国を長い時間を経て発展させるシュミレーションのゲームである。
数年前にCIVILIZATIONというPCのゲームにはまっていた。これは人類の誕生からギリシャ、ローマ時代を経て中世、ルネサンス、大航海時代、現代、宇宙の時代へと自国を長い時間を経て発展させるシュミレーションのゲームである。
延々と続く。1昼夜で終わるのは難しい。もっとも数千年をシュミレーションしているのだから当然と言えば当然だ。
このゲームはまず、一人の人間から始まり、最初の都市を建設する。そして食料を生産する。食料が増加すると人口が増える。逆に食料がなくなると餓死する人も出てくる。国を発展させるためには人口を増やして新しい都市を建設していかなければならない。さらに「進歩」を開発する必要もある。たとえば、「農耕」「牧畜」「青銅器」「航海術」などだ。この「進化」の開発には知識の集積が求められる。そのために、「書式」などの進化も必要だし、さらに「学問所」「大学」などの施設もあると知識の集積はさらに高まる。
しかし、自国のことだけにそんびりはしていられないのだ。世界にある都市は自国だけではない。蛮族の襲来もあるし、他民族が攻めてくることもある。ここに民族が生き残るための「進化」の競争が発生する。当然、マスケット銃を持っているよりは、マシンガンを持っている方が有利であるし、甲冑を着た騎士よりは現代の戦車の方がはるかに安心だ。戦争だけでなく、貿易などを通じた経済戦争もある。優れた製品を開発すれば、競争相手から金を得ることができる。金があればほとんどのものを買うことができる。
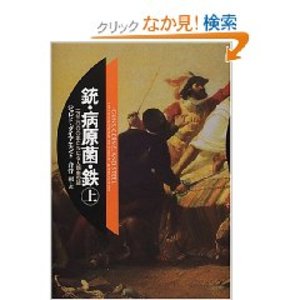 「銃・病原菌・鉄」を読んでいて思い出したのが、CIVILIZATIONだ。何かを始めるには人口を増やさなければならない。そのために農耕、牧畜を始める。そして保存できる穀物を収穫するとそれを腐らせずに保存する穀物倉庫を建設する必要がある。食料の備蓄ができれば、採集狩猟民として縷々転々とする必要はなくなり、モノの蓄積が可能となる。また、余剰食糧によって、食料を生産する人間ばかりでなく、大工、鍛冶、神父、教師など専門分野をもつ分業が可能となる。さらに、常備軍をもつこともできるようになったのだ。
「銃・病原菌・鉄」を読んでいて思い出したのが、CIVILIZATIONだ。何かを始めるには人口を増やさなければならない。そのために農耕、牧畜を始める。そして保存できる穀物を収穫するとそれを腐らせずに保存する穀物倉庫を建設する必要がある。食料の備蓄ができれば、採集狩猟民として縷々転々とする必要はなくなり、モノの蓄積が可能となる。また、余剰食糧によって、食料を生産する人間ばかりでなく、大工、鍛冶、神父、教師など専門分野をもつ分業が可能となる。さらに、常備軍をもつこともできるようになったのだ。
近代においてはアジア、アメリカ、アフリカの大半が欧米列強の植民地と化したが、その国力の差が、農業革命に発していたというのは新たな発見だ。
自分自身が食料を調達しなければならなかった狩猟採集民では新たな知識を獲得する余裕はなかったであろう。また、その必要性も感じなかったに違いない。国家間の果てしない知識獲得競争に必要なのは食べることに不自由しない人間だった。
人類の歴史は持てるものと持たざるものの不平等な戦いの歴史であり、その根本的な原因は農耕を開始したタイミングにあるとする本書には説得力がある。ゲームCIVILIZATIONはこのことを忠実に再現していた。
人類の歴史を見ても、見なくても、食べるために働くことから早期に脱却することが有利であることは明らか。しかし、現代では食べるためにより長時間の労働を強いられているのも事実。狩猟採集民から農耕民への転換は相当な労働時間の延長をもたらした。農耕民から工員、各種のサービス業への転換はさらに過酷な労働を強いている。所得と幸福度は比例しないというが、進歩がもたらすものはいいものばかりではないようだ。
しかし、ここにおいても進歩をせず、現状を維持するという選択はない。それは、ピサロに滅ぼされたインカ帝国、アメリカ人に虐殺された北米大陸における先住民、ならびに原子爆弾を落とされた日本のようになってしまうからだ。
米国は常に最先端を行っている。それは、報復を恐れるが由縁であろう。劣後すれば必ず相手にやられることを過去の自らの行動から熟知しているからだ。
内向きの国民と政治家を抱える日本はどうであろうか。総選挙の争点に持てる国への復帰を大きな争点にしてみたらどうだろうか。
「知識立国」これをキーワードにしては
みんなでCIVILIZATIONをやってみよう。
コメント