負けると思われる戦争は回避できるか?
毎年、夏休みになると太平洋戦争をテーマにしたテレビ番組が多くなる。大半が、平和の尊さと当時の無謀な政府と軍首脳陣に対する批判に終始している。当時の日本においては、ハルノートが米国からの実質的な最後通牒と捉えられていた。それを拒否して太平洋戦争に突入したのだが、ハルノートの受諾を選択したら日本はどうなっていたのだろうか
そもそも日本はなぜ、満州や中国に出て行ったのであろうか。日本では当時の8千万人の国民を養えなかったのである。女工哀史などにあるとおり、昭和初期の農村は娘を売っていた時代だ。簡単に言うが、実の娘を売り飛ばすというのはよほどのことだ。多くの兵士はそのような農村出身だった。農村から多くの人々が満州、ブラジル、ハワイへと移民した。好きで行ったのではない。国内に余裕があれば何も辺鄙な満州などに行く必要などない。暮らせるのであれば日本が一番いい国だった。日本に座して餓死するか、他人から奪うかの二者択一の選択だったのではないか。すでに大量の兵士が血を流したためにメンツとして撤退できなかったというような論調もあるが、すでに死んでいた人はいいのだ。その当時の国民をどう生かすかが問題だったのである。ハルノートの受諾は国民の大量の餓死を意味していたと思う。
太古の狩猟採集民で考えてみるとわかりやすい。狩猟採集で生活をしていた部族の住んでいた地域に採るべき獣や木の実がなくなったとする。新たな土地で獲物を探そうとするのを部族民や家族は反対するのであろうか。むしろ、早く食料を持って帰って欲しいと要求するのではないのか。争いになるから、ひもじくてもここで我慢しようなどとは考えないであろう。今食えている人たちは無謀な戦争だと客観的に言っているが、当時の国民は今とは違う。誰が、好きこのんで戦争をするだろうか。常識で考えたい。
私は戦争に賛成するわけではない。帝国主義などという難しい言葉を持ち出すまでもなく、単純な縄張り争いだったと思う。
日本人は日本の縄張りを侵そうとする他民族と民族の存亡を賭けて戦ったのだ。米英が中国は自分の猟場だから日本は出て行けと言ったわけだ。どう考えても勝てそうな喧嘩ではなかったが、お腹を空かせた家族のことを考えると、はい、わかりましたとは言えなかった。国内だけでは食わせられないからだ。だからこそ、準備も不十分で、これといった戦略もなかった。特別攻撃の実施、補給の不足ならびに装備の劣後は日本が計画的な戦争をしようとしていなかったことを物語っている。どちらかというと、破れかぶれだった。
日露戦争の際もさして条件は変わらなかったが、かろうじて勝ったことになったので今のような批判は聞かれない。むしろ、NHKが今年「坂の上の雲」を放映するようだが、おそらく、日露戦争に関して否定的な内容はないと想像される。簡単に言うと、勝てば官軍、負ければ…である。
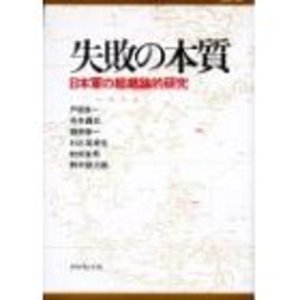 しかし、戦争をするからには勝たなければならない。「失敗の本質」は組織論としての日本軍の敗北の原因を分析した古典的な名著である。しかし、その著者も認めているように敗因はさらに高いレベルの国力の差に基づくものであった。総力戦という言葉は第一次大戦から出現していた。軍事以上のレベルでの競争だったのである。産業革命に100年乗り遅れた日本が如何にして米英を凌駕するかという国家的な戦略の欠如にあったと思う。鎖国の250年の重みは大きかった。しかし、旧ソ連は革命後の数次にわたる5カ年計画により、第二次大戦の開始時にはすでにドイツを上回る重工業国に脱皮していた。戦車や航空機の生産量はドイツの数倍におよび、その結果物量でドイツを圧倒できたのである。
しかし、戦争をするからには勝たなければならない。「失敗の本質」は組織論としての日本軍の敗北の原因を分析した古典的な名著である。しかし、その著者も認めているように敗因はさらに高いレベルの国力の差に基づくものであった。総力戦という言葉は第一次大戦から出現していた。軍事以上のレベルでの競争だったのである。産業革命に100年乗り遅れた日本が如何にして米英を凌駕するかという国家的な戦略の欠如にあったと思う。鎖国の250年の重みは大きかった。しかし、旧ソ連は革命後の数次にわたる5カ年計画により、第二次大戦の開始時にはすでにドイツを上回る重工業国に脱皮していた。戦車や航空機の生産量はドイツの数倍におよび、その結果物量でドイツを圧倒できたのである。
目先の軍艦や大砲を作ることに熱中するのではなく、その大量生産と科学技術の向上をさせる政策を高次に計画していかなければならなかった。多額の予算と時間を費消した戦艦大和は数時間で沈んだ。レーニンと日本の指導者の差であろうか。
さらに軍事のレベルにおいてもアングロサクソンのやり方は違うのだ。米国は明治時代から「オレンジ計画」を策定し、日本を仮想敵国として作戦計画を練っていた。マッカーサーの採った戦略はほぼ、このオレンジ計画に沿ったものであった。その長期的な視野と演繹的な几帳面さに対抗して行かなければならない。
では話を戻してハルノートを受諾して日本が中国から撤退したとしよう。米英ならびにソ連はそれで満足したであろうか。否であると思う。及び腰になった相手に対しては徹底的にやってくる。台湾、朝鮮への権益も主張してきたであろう。さらに日本の植民地化も目論んだかもしれない。いづれにしてもその際に戦争になったのである。
ブッシュがイラク戦争を始める際に核兵器を口実とした。太平洋戦争では絶対に日本がのめないであろうハルノートを突きつけて日本に先制攻撃を掛けさせた。彼らにとっては戦争はゲームなのだ。新世界において先住民を虐殺・部族を全滅させながら国を拡大して来た歴史が物語っている。平和的な手段で国を築いて来たのではない。国民の血で国を築いてきたのである。オバマはアフガニスタンを狙っている。中国は台湾を狙い、太平洋への進出をもくろんでいる。
日本人は戦争を感情論で整理しようとしている。それでは進歩がない。大競争をやっているのだ。持たざるものが持てるものと仲良くできる訳がない。パワーバランスで均衡点が得られる。パワーがなければ大国のいいなりになるしかない。その前提で外交を考えないと国益は守れない。
しかし、持たないものは常に譲歩しなければならないのであろうか。そうではない。米国は日本との戦争でこれほど手こずるとは思っていなかったのである。ペリリュー島、硫黄島、沖縄の戦いで思い知ったはずだ。日本人は強いのだ。
喧嘩に負けてはならないが、負けることもある。しかし、拳骨は隠しても準備しておいていつでも繰り出せるようにしていなければならない。先に殴られて気絶してからでは遅いのだ。その意味でオバマの核軍縮を本気であると捉えるのはおめでたいとしかいいようがない。核は先制攻撃されたら後がないのだ。
負けるかもしれないと思っても戦争を選択する必要はある。なぜなら、勝負はその場だけではないからだ。弱腰にはさらなる譲歩が求められる。
コメント