避けられるリスクと避けられないリスク
真夏の暑い夕方、仕事を終えた私は上司を助手席に乗せて車で帰途についていた。まだ明るかったと思う。つけていたラジオがさりげなくジャンボジェットがレーダーから消えたというニュースを流した。隣に座っていた上司が「大変だ!」と言ったのを覚えている。1985年8月12日月曜日の夕刻だった。
毎年8月12日になるとこの御巣鷹山への慰霊登山のニュースが放送される。今年はすでに24年目になる。
毎年そのニュースを聞いて私もあの暑い夏の夕暮れを思い出す。上司の言った言葉を。
空中にいる航空機が飛行場に着陸せずにレーダーから消えたということは墜落を想像させた。あとから判明したことだが、当時私が勤務していた青梅市の近くの御巣鷹山に墜落したのであった。
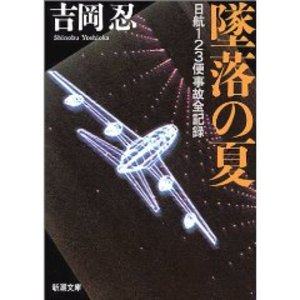 123便は18:12に羽田空港を離陸し、12分後の18:24に伊豆半島東海岸上空で垂直尾翼が欠落し、ダッチロールをしながら焼津、大月上空を経て18:58に墜落した。その間わずか46分。しかし、乗客にとっては…
123便は18:12に羽田空港を離陸し、12分後の18:24に伊豆半島東海岸上空で垂直尾翼が欠落し、ダッチロールをしながら焼津、大月上空を経て18:58に墜落した。その間わずか46分。しかし、乗客にとっては…
下田沖は内航海運の要衝であるが、空も同様である。上空は飛行機がひっきりなしに飛んでいる。そこで垂直尾翼を落っことしたのだ。
「墜落の夏」には本人と家族について追跡している。乗員乗客524名のうち死亡は実に520名。生存者は最後尾に乗っていたわずか4名だけであった。この事故の結果乗客の関係世帯401世帯(夫254名、妻58名)がどうなったか。
遺族は891名にものぼる。
一家全員死亡22世帯、母子家庭189世帯、妻だけ37世帯、子供だけ7世帯
悲惨な事故であった。
機内で書かれた遺書が数通公開されている。おそらく墜落するであろうことは予期して書いたものと思われる。自分ではなんともすることができない悔しさがにじみ出ている。しかし、あのような状況の下でこのように書ける人の遺書は本当の気持ちを綴っていると思う。
「パパは本当に残念だ。きっと助かるまい…
本当に今までは幸せな人生だったと感謝している」
あの事故は防げたのであろうか。
否であると思う。
後知恵ではなんとでも言えるが、ランダム性は回避できない。当時の日本の人口1億2千万人からすると25万分の1の確率であるが、本人にとっては100%の確率。
また、発生したあとでそんなことを考えても始まらないではないか。
本来は次の便に乗るはずだったが早く空港に着いたために123便に乗った人もいたという。
回避できるリスクと回避できないリスクがある。飛行機に乗るのをやめても回避できない。移動する乗り物に絶対の安全はない。できるのは回避できるリスクを回避するだけだ。たとえば生命保険の加入は間違いなく遺族の財務的なリスクを回避する手段といえる。タバコをやめてニコチンと一酸化炭素の体に対する影響を排除するのもその一例。肥満を解消して生活習慣病を回避するのもそうだ。
そう考えてみると回避できるリスクはわかりやすいものが多い。わかっているけど回避行動の実行を躊躇することが多い。
推測に過ぎないが、あの状況下で「今までは本当に幸せな人生だった。」と書ける人は回避できるリスクを回避してきたのであろう。だから回避できないリスクに陥ってもそう考えることができるのかもしれない。
気づいたことに対しては即対処するという選択がわかりきった(回避できる)リスクを回避する数少ない手段と言える。しかし、それがなかなかできない。そんな時には御巣鷹山を思い出して避けられないリスクは避けられないこと。したがって、自己実現のためには避けられるリスクを回避するしかないことを考えた方がよい。
コメント