フォードのミームがトヨタへ
「麦のハンドル」Today and Tomorrow
by Henry Ford
ジャストインタイム(トヨタ式生産システム)の母といわれる大野耐一がその発案のきっかけだと話したのがこのヘンリー・フォードの自伝だったという。なるほど、今とあまりコンセプトがかわらないことを100年前に実施していたのだ。いや、むしろ、100年後の我々がフォードの考え方を乗り越えられていないか、むしろ、退化している部分もあると思われる。
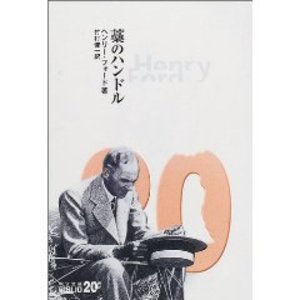 ヘンリー・フォードの哲学はシンプルかつ明確であった。小型でシンプルで安価な乗用車と従業員に対する高賃金(賃金動機)の支給。その前提とした徹底的な大衆(顧客)指向。
ヘンリー・フォードの哲学はシンプルかつ明確であった。小型でシンプルで安価な乗用車と従業員に対する高賃金(賃金動機)の支給。その前提とした徹底的な大衆(顧客)指向。
「会社は何らかをサービスするようにデザインされなければならない。」「現状を出発点として、大衆が企業を成り立たせてくれるようにことを運ぶ工夫をすればよい。結局、大衆が、大衆のみが、企業を作ることができるのだ。」
20世紀初頭の米国には自動車を購入する購買力を有する消費者が少なかった。だから、まず、低価格の自動車を生産する必要があった。さらに消費者の所得を増やすことができればさらに販売台数は増大する。フォードはその双方を一企業人として実現したのだ。前者は企業人としてごく当然のことだ。さらに商品の価格を下げるために、従業員の賃金を切り下げ、工場をより低コストの海外へ移転してしまう。その結果、さらに購買力が低下して自社の商品が売れなくなるのである。まさに、悪魔のサイクルに陥ってしまっている。
フォードは資本家、金融機関を嫌悪する。企業価値は株価では計れないという。そういわれてみれば、企業価値はミームであり、金銭で評価できないものが大半である。しかし、株価の上下で経営者が評価されると信じている人が少なくない。しかし、そのような経営者は自分の金銭的な利益を得るための便法として株価を利用しているに過ぎない。株を持っていない消費者からすると株価などどでもいいのだ。問題は提供されるサービスの質と価格であり、フォードは冷静にその事実を理解していたといえる。もっとも、株価がわかるのは上場企業だけである。GDPの過半は中小企業が上げていることを忘れてはならないだろう。
また、彼には政府の補助金に頼ろうとする気持ちは一切なかった。彼は政府に対する依存心を厳しく戒めている。政府には与えられたもの以上に与えるものがない。政府に依存する国民は思考と努力を放棄して常に政治的な解決策に期待をかけることとなり、その国民自体が弱くなる。そのような気風を煽る政治家や労働運動家を批判する。彼らは自分の商売として問題を作り出すのだ。昨今の日本をみたら彼はなんというだろうか。そういえば、米国において民主党のオバマは医療保険導入を図っているが、意外にも反対勢力が多いと報道されている。やはり、米国は自由(税金・社会保険料からも)な国であり、国民の自立心も高いと見える。
さらに、余暇の重要性を説いている。持っている金を使わないで何もしないことを人生の浪費と表している。余暇もなければ金を使う時間もないではないか。不況時とはいえ、週休2日制も導入しているのだ。よい循環と悪い循環の差がここにある。最初のひと転がりが大事だ。
フォードをこのように強くしたのは何であろうか。自分の信念を貫くことができる強さ。登場するタイミングは異なるがGMのアルフレッド・スローンの哲学とは全く異なる。ずっと素朴で強いのだ。
大野耐一はフォードのミーム(知識の複製子)であった。過去の知識の吸収とその模倣は知識の複製には不可欠な選択である。今もフォードのミームは生き続けている。
<年表>
1908年 T型フォード発売 825ドル
1914年 ラインによる生産体制開始
490ドルに値下げ。
最低賃金を2ドルから5ドルへ引き上げ
1923年 年産200万台突破
1926年 週休2日制導入
累計生産台数1300万台突破
本書発行
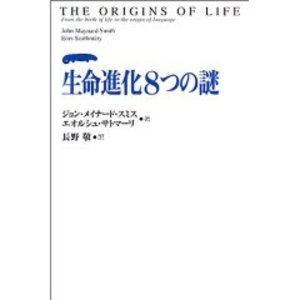
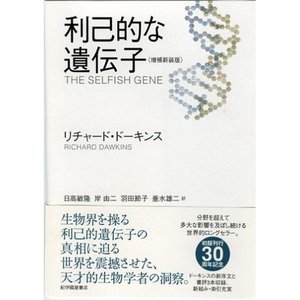
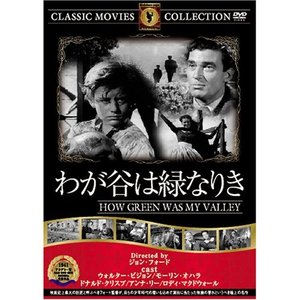
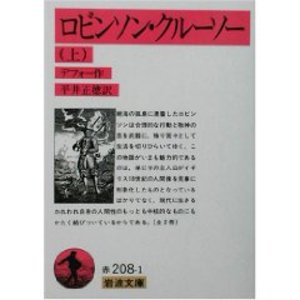
最近のコメント