起こったことに理由がつけられない理由
理由がわかってもしょうがない場合もある理由
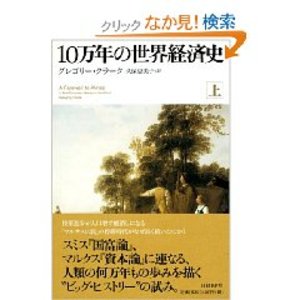 30年前にアルビン・トフラーが「第二の波」と言った産業革命はなぜ起こったのか。「10万年の世界経済史」でグレゴリー・クラークは長々と説明をしたが、結論を言うと産業革命が起こった理由は特定できなかった。様々な理由を上げることはできるが、単独の要因ではあり得ないし、複数のもっともらしい要因を組み合わせてもその組み合わせは非常に多岐にわたる。多くの要因を重ねていくと必然的に理由の特定から離れていく。あるいは意味がわからなくなる。1800年以前のマルサス的経済学のように土地と人口の相関では説明できないほど世界は複雑化してしまった。
30年前にアルビン・トフラーが「第二の波」と言った産業革命はなぜ起こったのか。「10万年の世界経済史」でグレゴリー・クラークは長々と説明をしたが、結論を言うと産業革命が起こった理由は特定できなかった。様々な理由を上げることはできるが、単独の要因ではあり得ないし、複数のもっともらしい要因を組み合わせてもその組み合わせは非常に多岐にわたる。多くの要因を重ねていくと必然的に理由の特定から離れていく。あるいは意味がわからなくなる。1800年以前のマルサス的経済学のように土地と人口の相関では説明できないほど世界は複雑化してしまった。
その理由がわかれば、どこの国でも産業革命が起こせることになり、サハラ以南のアフリカやニューギニアなどの地域はなくなるはずだ。しかし、英国において18世紀の中盤から始まった産業革命に対してこれらの地域は300年後の現在でも第一の波にも乗れていない。産業革命は起きていますよと言っても、どうやってそれを実現するのかはその地域、国によって違うのである。その個性にあった処方箋の内容とタイミングがあるのだと思う。
自然科学と同じように社会科学が安易に因果関係を語らない方がよい。本書が不本意ながらもそれを立証している。本書には英国における様々なデータが非常に充実している。これだけの統計が残っているのはさすが大英帝国だ。しかしながら、様々なデータがなんらかのまとまった理由を構成することがないのだ。データはみんなバラバラ。考えてみれば事実というのはそのようなもの。無理にまとめようとすると意図的に何かを無視し、あるいはないことをさもあったかのように書かなければならない。マスコミの短兵急な結論の出し方を見慣れていると驚かないが、その乱暴さにみんな慣れており、結果としてそのような主張に対して無視という静かな反乱をしていることが多い。
しかし、そもそも未来の予想に必ずしも過去の経験則を必要としなければ、無理に原因を追及する必要もない。
さらに、もし、ある社会的な事象の発生原因が判明しても再現性があるとは限らない。というのは、わかっていてもできない場合もあるということである。というか、むしろ、できない場合が多いというべきか。
英国で蒸気機関車による鉄道が開通したのが1825年。世界はびっくりしたはずだ。その後、アメリカに鉄道が敷設されるまで5年、フランスでは7年を要した。メキシコに至っては48年後だ。これはわかっていてもできないケース。受け手のニーズと受け入れる環境の有無が解決策の実現のタイミングを左右する。
一方、わからないからできないのは同じくワットが発明した蒸気機関の活用法だ。ワットは鉱山におけるポンプを動かすために蒸気機関を改良した。1769年に熱効率のよい蒸気機関は開発されたが、ポンプ以外にその蒸気機関の使い道が長い間気づかれなかった。蒸気機関イコール ポンプだったというわけだ。
世界初の蒸気船であるフルトンのクーラモント号のニューヨークにおける初航海が1807年であるからワットの蒸気機関開発後38年。スチーブンソンがストックトン・ダーリントン鉄道を走る蒸気機関車ロコモーション号の完成には実に56年の年月が必要だった。開発期間が長かったというのもあったが、蒸気機関の活用法を長い間思いつかなかったという要素が大きいのである。解決策はあるが、その問い(課題)がわからなかった好例。
再現可能性は前提条件の類似性に依存する。DVDはそれを再生するプレイヤーによって何回も再生ができる。それはDVDのディスクとプレイヤーの規格が相互に一致することを前提とする。ipodやMDプレイヤーではDVDは再生できないのである。そのために規格が作られて標準化が行われる。だから、鉱山のポンプという似たような環境(規格)においては比較検討することができるのだが、馬車や帆船はポンプとは全く前提条件が違ってみえて、アナロジーが効きにくかったのであろう。
一方、多数の人間が存在する社会や二度と同じ水が流れることのない川のような自然に規格や標準化ができるだろうか。
それらは前提条件がすべて違うように見える。だから社会(人間の世界)や自然に対してアナロジーで知識を活用することは意外と難しいと思う。後知恵ではなんとでも言えるのだがその場にいたら見えないのだ。
このように、起こったことに理由を見つけることは簡単ではない。さらに、その理由が見つかったとしてもそれを他の課題に活用することも簡単ではないのだ。簡単ではないが、長い時間がそれを解決することがある。急いでも無駄なのかもしれない。そのうちに解決するであろうという程度が一番適切な感覚なのかもしれない。
それでも人間は理由を探し続ける。それは人間の性かもしれない。それを止めることはできない。でも考える葦はそれに知的なおもしろさを強く感じるのだ。結果がどうであれ。役に立つか、立たないかは二の次。この性に対して選択の余地はない。それが人間を人間たらしめているものだからだと思う。
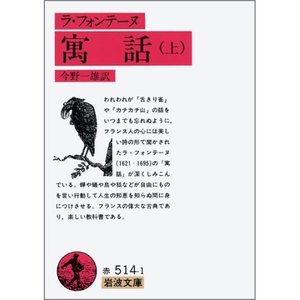


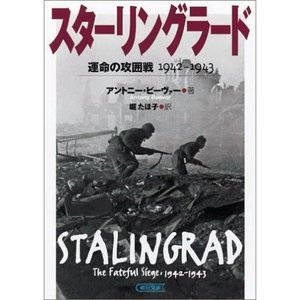
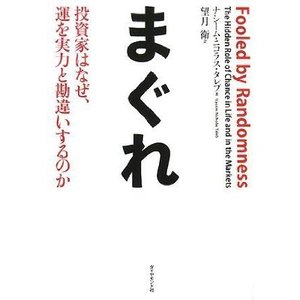
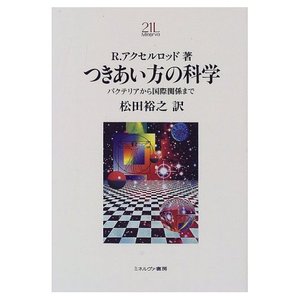
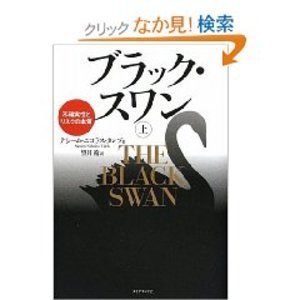
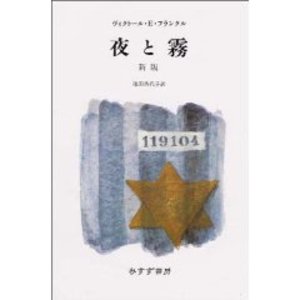
最近のコメント