私でも夏の間は鳴いてるであろうキリギリス
(前回からのつづき)
3年間過ごした札幌では蝉の鳴き声を聞く機会がなかった。真夏でも大通り公園のビアガーデンでビールを飲んでいると思わず上着を着るような場所柄だ。
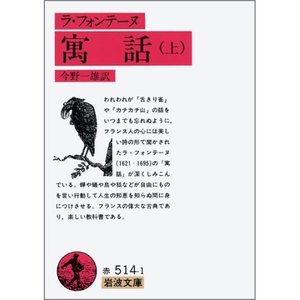 もともとイソップが残したのは「蝉と蟻」という寓話。岩波文庫の「イソップ寓話集」もそうであるし、同じく岩波文庫のラ・フォンテーヌの「寓話」も「蝉と蟻」だ。
もともとイソップが残したのは「蝉と蟻」という寓話。岩波文庫の「イソップ寓話集」もそうであるし、同じく岩波文庫のラ・フォンテーヌの「寓話」も「蝉と蟻」だ。
では、なぜ日本では本来「蝉と蟻」という寓話が「蟻とキリギリス」という全く別物として話が普及しているのだろうか。その原因だけでなく、その変遷が解釈にも大きな影響を与えているのだ。
イソップ寓話は江戸中期から日本に翻訳されていたらしいが、本格的な導入は明治になってからのようだ。明治は英国版が日本語訳されて広まった。その英語版は「蝉と蟻」ではなく、「蟻とキリギリス」だったのだ。どうして蝉がキリギリスになってしまったのか?
実は英国には蝉がいなかったらしい。(今でもそうかな?)私の札幌の経験に符合する。札幌の子供も図鑑でしか蝉を見たことがないだろう。ましてや虫籠と採集網をもって蝉を捕った経験のある子は少ないと思われる。子供に見たこともない昆虫の話をしても実感が湧かないだろう。英国で夏に歌って踊っている代表的な虫はキリギリス(Grasshopper)だったようだ。それで、英国にはいない蝉をキリギリスに置き換えたのだ。ラ・フォンテーヌは仏人。フランスには蝉がいたようだ。だからラ・フォンテーヌの「寓話」は「蝉と蟻」。それはそうだフランスはファーブルの国だ。ファーブルは英国に生まれたら昆虫記を書いただろうか?フランスに生まれてよかったのである。
話を戻す。蝉であれば迷いがなかった。子供でも夏に蝉の亡骸が転がっていることを知っている。しかし、キリギリスの亡骸を見たことはあるだろうか。これがこの寓話の解釈を左右することになる大問題となったのだ。
成虫となった蝉の平均余命はどうであろう?平均余命は普通「年」で表示される。しかし、現在7月の下旬でも蝉の亡骸が随所に見られる。子供でも成虫となった蝉の寿命は長くても1~2週間と知っているのだ。しかし、キリギリスはいつまで生きると問われても即答できる人は少ないだろう。彼らは越冬するのだろうか?
「蟻とキリギリス」の話はキリギリスが夏の間にまじめに働いて食べ物を貯蔵していれば、冬に困らなかったということが前提の話。もともと困らないのであれば責められるいわれはない。キリギリスは不真面目な「人」の代表として責められて来た。
しかし、イソップが残したのは「蝉と蟻」。彼はギリシャの人で蝉をよく知った上で「蝉と蟻」を作ったのだ。蝉は成虫となって長くとも1ヶ月は生きない。冬を迎えることはないのだ。
とすると、夏の間に歌って踊っていた蝉の行動はどう評価されるのだろうか。
私は子孫を残すために(彼らには我々と違って一夏しかチャンスはないのだ)彼女に対して懸命に求愛を歌う蝉を責めることはできない。まさに命の歌なのだ。私でも歌うであろう。明日の命もわからない状態。食べている場合ではないのだ。
ということで、イソップは現在の日本における解釈とは逆説的なメッセージを込めていたと思われる。昔の人間の短い人生にとって今日を幸せに送れることが最重要だったのである。女性が平均6人の子供を産んでも2人しか成人しない時代だったのだ。平均寿命は1800年の英国でもわずか37年だったのだ。イソップの時代の人は夏を何回過ごすことができたのだろう。
<歌い上げた蝉の勇姿>
では、キリギリスはどうか。やはり越冬する者はいないようである。
英国はキリギリス。ではポーランドのイソップ寓話では?
「蟻とコオロギ」だそうである。コオロギとなると話は別だ。
現在と将来の選択に「蝉と蟻」の話は重要な指針を与えてくれる。
でも、あるかないかわからない明日とそれ以降よりも今日の方が確かなのは間違いない。


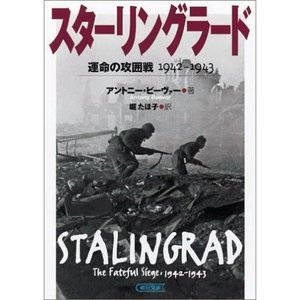
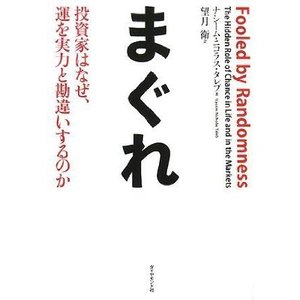
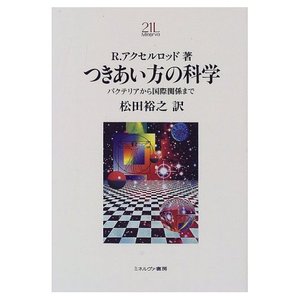
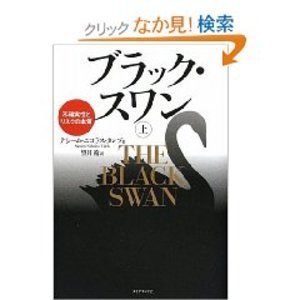
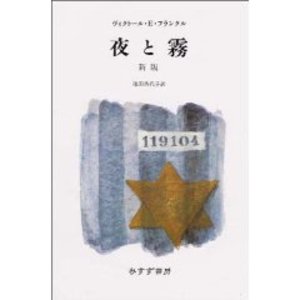

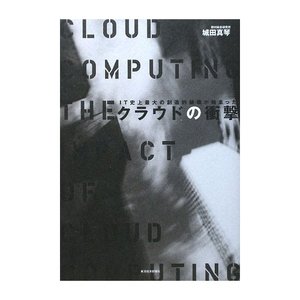
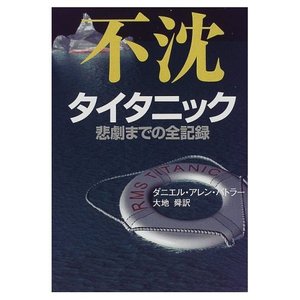
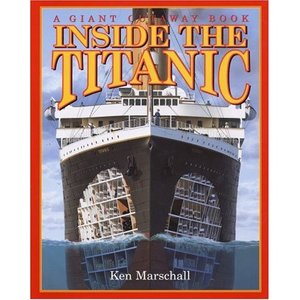
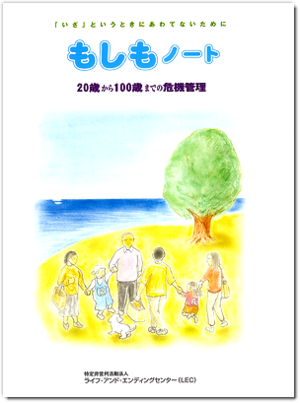
最近のコメント