「政策の再考はなされなかった。なぜなら、統治グループにはある目的のために検討を重ねる習慣はなかったし、頭の上には国王をいただき、お互い同士はうまくいっていなかったからである。」
バーバラ・W・タックマン
マーケティングの世界でもone to one と言われるように、
交渉する際には、相手をよく知っていた方がよいに越したことはありません。
たとえば、好きなもの(こと)、嫌いなもの(こと)、価値観、仕事、財産、家族、趣味などです。
しかし、そうとは思いながら、あえて誰にでも同じような対応をすることがあります。
それは、相手が誰であろうと、自分を前面に押し出すことによります。
基本は、相手を知る(相手の話を聞く)ことが先であることは間違いありません。
運命の1941年12月8日 日本は真珠湾を奇襲攻撃し、対米戦を開始しました。
対米戦を回避する外交努力が続けられており、日本側から提示した乙案が受け入れられる可能性がありました。
しかし、11月26日に国務長官のコーデル・ハルから提示されたハルノート(両国の協定案)の内容を見て、日本は受け入れることができないと判断して、開戦の決断に至ったと言われています。
そして日本は、東条首相の言うところの、一かバチかの「敵の死命を制する手段がない状態」で開戦せざるを得なかったのです。
米国の強硬な姿勢は、ドイツと交戦している英国を救わなければならないと考えていたルーズベルトの意向が強く反映していたと言われています。その意味では、日本はルーズベルトによって、開戦に誘導されたと言えます。
しかし、本当に日本に他の選択肢はなかったのでしょうか。
 太平洋戦争で、日本を開戦に踏み切らざるを得なくさせた米国ですが、実は、その米国の英国に対する独立戦争も似たような経緯で始まっていたようです。
太平洋戦争で、日本を開戦に踏み切らざるを得なくさせた米国ですが、実は、その米国の英国に対する独立戦争も似たような経緯で始まっていたようです。
アメリカの植民者に本国英国に対する独立戦争に踏み切らざるを得なくさせたのは、英国国王であったジョージ三世(右写真)とその内閣そして議会でした。
当時の植民者は本国から自由でいたいという気持ちは強かったものの、独立などはつゆも考えておらず、国王に忠誠を誓いながら、英国の自治領としていたかったようです。
1775年4月19日にアメリカのコンコードにて植民者と英国本国軍の間に戦闘が発生し、独立戦争の火ぶたが切って落とされました。
その後、1776年に独立宣言をし、6年間の長期の戦いを経て、1983年にパリ講和条約により、正式に独立を勝ち取りました。
アメリカの独立戦争のきっかけは、本国英国から植民地アメリカへの課税問題でした。
1763年に終わった7年戦争により、英国はフランスからケベックと西インド諸島の大半の領土を獲得しましたが、莫大な政府の債務が残りました。
そのため、植民地に対する課税を強化していったのです。
もともと、英国の圧政を避け、自由を求めて自分自身のリスクで植民している開拓者からすると、本国から課税されるいわれはないのです。そして、アメリカにはすでに250万人もの植民者がいました。
植民者の代弁者は「代表なければ課税なし」と、アメリカの要望を本国の政府と議会にたびたび要望しましたが、受け入れられませんでした。
むしろ、ジョージ三世と本国政府は植民地に強圧的な態度で臨むようになります。
本国においても、大ピットや、エドマンド・バークは、強圧的な態度が植民地を離反させ、英国が植民地を失うリスクがある。
さらに、多少の税の徴収よりは、広大な植民地を維持して交易をした方が国益にかなうと主張しました。しかし、彼らの意見は取り入れられなかったのです。
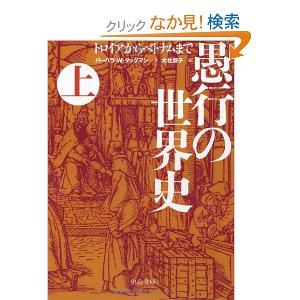 なぜなのでしょうか?
なぜなのでしょうか?
バーバラ・W・タックマンは「無知」であるとしています。交渉する相手を知らなかったということです。
当時、大半の英国人はアメリカ人と言えば、黒人であったと思っていたそうです。この一事をみても、判断の根拠となる事実認識に大きな狂いがあったことが分かります。
しかも、本国が一等国で植民地は二等国という根拠のない偏見が植民者を軽視しました。
また、アメリカとの紛争が激化した1763年から1775年の間に、実際にアメリカに赴いて現地の実情を把握しようとした閣僚が一人もいなかったと言います。
大西洋を渡り、インディアンや他国の植民者と戦いながら自分で国を切り開いた移民たちは非常に自立心が強く、プライドが高かったといいます。
また、ミニットマンと言われた民兵も猟で生活する必要性から、射撃の腕前は、プロの兵士より高い者が少なくなかったそうです。組織的な行動の訓練はしていませんでしたが、ゲリラ戦的な戦いでは軽視できる相手ではなかったのです。
しかも250万人という人口に広大な国土。とでも数万の軍隊で征服できる土地ではなかったのです。
ジョージ三世とその政府、議会は、アメリカのことを何も知らずに課税という重要な政策を推進して行ったのです。
その結果は、アメリカを失うという英国にとっての破局的な結末でした。
そして、タックマンによると、日米開戦も独立戦争と同じ状況であったというのです。
ハルノートを受諾して中国から撤退するか、米国と開戦するかという選択肢の他に、第三の選択肢の存在を指摘しています。
第三の選択肢とは、日本がオランダ領東インド諸島に進駐して必要な石油などの資源は確保するが、アメリカには触れないでおくという選択です。
この選択は、日本の背後(米国領フィリピン)に未知数の残す結果にはなったかもしれませんが、米国と即 交戦するよりもはるかにましだったはずだというのです。
確かに東インド諸島を確保できて、米国が参戦しなかったらベストのシナリオです。しかし、日本政府はそれができるとは考えていませんでした。米国は必ず参戦してくると読んでいたのです。それであれば直接米国の軍事基地を奇襲攻撃しようと。
しかし、第一次大戦後の米国は国民を戦争に行かせるのに強い抵抗感を持っていました。当時、議会において、1年期限の徴兵法の更新が決定されたのは、わずか1票差の際どい多数決による結果だったことからもそれは証明されています。
さらに、米国民の気持ちとしては、アメリカ本土はヨーロッパともアジアとも独立した大陸であり、広い大西洋と太平洋が堀となり、他国から侵攻される恐れがまずないのです。
また、米国は大恐慌の影響が色濃く残っていたとはいえ、日本などにくらべると遙かに豊かな生活を送っていたのです。そんな幸せな生活を捨てて戦場に行きたい若者が多数いるとは思えません。
だから、ルーズベルトは米国民を動かして、ヒトラーと戦う英国の求めに応じることができなかったのです。
アメリカ人を戦争に引き込むことができる方法はたった1つ。それはアメリカの領土に対する攻撃だけだったのです。
日本人は自分たちの基準でアメリカを判断して、アメリカ政府はいつでも好きなときに自国を戦争に駆り立てられると思いこんだのです。
それは、日本では天皇のために死ぬ教育をしてきたため、天皇の臣民である国民はその命令一下 戦場に赴くのが当たり前だったからです。
山本五十六提督の意図に反し、真珠湾に対する攻撃はアメリカ国民の意識をくじくどころか、かえって国を挙げて戦争に立ち上がらせてしまったのです。
したがって、日本は対米戦の危険を犯さないでも東インド諸島を獲得できた可能性があるのです。東インド諸島が確保できれば当面の対中国戦は継続できたのです。
もちろん、その後のことは分かりません。
ジョージ三世と英国人がアメリカ人を知らずに強攻策に出てアメリカという植民地を失ったのに対して、日本人はアメリカ人に対する「無知」で国(本国)を失ったのです。
相手を知るというのは簡単なことではありません。
でもその努力を怠ってはならないことが教訓として残りました。
英国が米国を独立させ、米国が英国を救うために日本を参戦に追い込みました。
その結果は、常に相手に無知な側に損害をもたらしたのです。
(56の符合)
米国独立の際の大陸会議のメンバーが56名で、真珠湾攻撃計画を立てた連合艦隊の司令長官が山本五十六であったのは妙な符合?
最近のコメント