サービスがFree(無料)でいい理由、Freeのオマケが必要な理由
日曜日なので夕方にいつものスーパーに買い出しに行ってきた。スポーツクラブの帰りだ。
入り口から果物、野菜、魚、肉、そしてお総菜と並んでいる。単身赴任の身分としてはこのお総菜コーナーが買い物のメインイベントだ。
お総菜も揚げ物が多いので健康にはどうかと思うが、簡単なのでつい手が出てしまう。トンカツ、メンチカツ、コロッケ、鳥の唐揚げ、そして各種の天ぷらがいつも通りにならんでいる。
しかし、今日は少しこのコーナーに人が多いようだ。なんだ?と近寄ってみると、鳥の唐揚げが半分に刻んであって試食用として提供されている。少なくないお客さんがそれを楊枝でつまむと、「あまり味が濃くなくていいわね。」などといいながら唐揚げのパックをかごに入れていく。このような風景はよく見られるものの、やはり不思議な気がする。それは、無料の試供品がなければ、買わなかったであろうお客さんが少なくないだろうからだ。
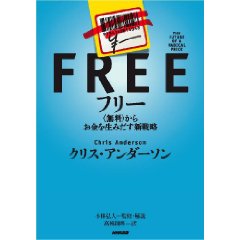 Free(無料)にはいろいろな形態があるが、唐揚げのような物質(アトム)がデジタル(ビッド)に移行することによってFreeの経済が拡大している。
Free(無料)にはいろいろな形態があるが、唐揚げのような物質(アトム)がデジタル(ビッド)に移行することによってFreeの経済が拡大している。
クリス・アンダーソンは“Free(フリー)”に4つの基本形を上げている。同氏はマーケティングを全く違う切り口で整理してくれた。ロングテールに続く「発明」ともいうべき著作だ。
その第一が「直接的内部相互補助」だ。言葉は難しいが、簡単にいうと消費者の気を引いて他のものも買ってみようという気にさせるというものだ。
典型的な例としてジレットのひげそりがある。T字のホルダーはただ同然だが、その後どうしても必要な替え刃はえらく高い。
アトムがあるものはわかりやすいが、ビッドはどうであろうか。
日本においては「サービス」は無料という意味で捉えられていた。サービスはアトムを伴わない無形のものなので代金が請求しにくいと思われている。
たとえば、企業が大学教授に専門的なことを相談しにいく場合。よくわかっていない企業人はアトムがないためにFree(無料)だと誤解して謝礼も置かずに帰ることもあるらしい。
税務相談も法律相談も時間単位のフィーになっているが、士業の先生方も実際はフィーを取りにくい。
顧問契約、具体的な税務申告などでサービスのフィーを回収することが少なくないようだ。
確かに、顧客にとって相談自体は手段に過ぎず、目的は問題の解決である。そのため、目的に達しようがしまいが、金を取るということに納得感が欠けるのも事実。
士業ならまだよいが、コンサルタント(様々いるが)などとなると、フィーを取るのは簡単ではない。セミナーの講演料も同様だ。
今までは専門知識を提供するにもかかわらず、フィーがとれないことがおかしいと思われていたのであるが、実はおかしくないのではないかと思い始めた。
クリス・アンダーソンの主張を聞いていると、むしろ、日本人のいうところのサービスはそのままFreeでよいのではないかという気がしてきた。
子どものころ、近くの公園で紙芝居を見たことがある。おじさんが自転車に紙芝居を積んでやってくる。子どもが数人集まってくると、今日の演題を説明する。そして、始める前に飴とか、煎餅とかの駄菓子を子どもに売るのである。当然買わない子どもは見ることができない。子どもの目的は両方なのだが、どちらかというと、紙芝居なのだ。
ここが「サービス」はFreeなのかという問題なのだが、おじさんは紙芝居などしなくても駄菓子が売れればそれに越したことはないはずだ。しかし、駄菓子だけならべても子どもが買ってくれないのだろう。それはお店があるわけでもないし、自転車で来ているのでは、大した種類の駄菓子があるわけでもない。そこで紙芝居というサービスをFreeで提供して駄菓子を売っているのである。子どもの主目的は駄菓子ではなく紙芝居なのだ。だから、おじさんは、駄菓子屋のおじさんではなく、紙芝居のおじさんということになっている。
また、私は年に2回歯石の掃除に歯科医に通っている。おかげさまで中学生1年以降は虫歯になったことがない。(奥歯は小学生のときにすでに虫歯になっているという意味だが)
80歳まで20本の歯を残すことを目標に3食のつど歯磨きをしている。しかし、どういう訳か歯石はついてしまう。
以前、知り合いの歯科医にほめてもらおうと思って、毎食後の歯磨きと年2回の歯石の掃除の話をしたところ、あなたのような人が歯医者にとって一番儲からないんだと言われてしまった。
歯石の掃除は、先生に歯のチェックをしてもらって問題がないことが判明してから歯科技工士の方が約20分かけて丹念にやってくれる。終わってみると歯の間がスースーするのでいつも不思議な気がする。毎日3回もどこを磨いていたのかと。
それでわずかに3千円程度だ。これでは先生の儲けはないだろう。
しかし、ご丁寧に半年毎に歯石のチェックのご案内をはがきでいただいている。
これは、実質的なFreeではないか。
毎回、先生は診査の際に私の口の中をのぞき込みながら、「何か変わったことはありませんか?」とお聞きになる。いつもは「なんともありません」と答えるのであるが、あるときに「奥歯が少し動くような感じがするのですが…」と言ったところ、先生のなんとうれしそうな顔!
即座にレントゲンをとることになった。
結果としてはなんともなかったが、このように実質的なFreeで定期的に診断をしていれば、いずれ歳を取れば、治療が必要になり、有料の顧客になるのであろう。
また、自動車の新車購入の際の3年間の点検パックも同じことだろう。料金先取りで、少なくとも3年間はその販売店に通うことになる。結果として車検時もしくはその前に新たな販売タイミングを掴む可能性もあるはずだ。
逆に顧客の立場で考えてみてもFreeのサービスはいいものだ。
しかし、それはFree(無料)だからという単純な理由ではない。
その第一は、歯科の椅子に寝転んでいい大人があーんっと口を開けているのも浮き世ばなれしている。他では味わえない感覚だ。マイカーの1年点検の際に広いショールームで展示車を見ながらコーヒーを飲むのもまたしかり。
Freeと言いながら、それなりのサービスが提供されているのである。
第二は、顧客サイドはそのサービスが全くのFreeではないことを理解しているということだ。
顧客は今はFreeであるが、いつか料金を取られるとか、またここで買い物をすると思っている。その結果、販売サイドの借りにならないことがFreeのサービスを受ける心理的な抵抗を減らしている。
スーパーやデパ地下で試食品に手を出すのは、ほとんど買おうとしている、あるいはいつかは買おうとしているからだ。試食品がそのタイミングを少しだけ早くしただけだ。
試供品を食べまくって満腹になろうという人は珍しいのだ。
クリス・アンダーソンのおかげで、このように身近に実に多くのフリーがあるのに気がついた。
本来の売り上げにつなげるために、無料(Free)で「サービス」する。
そのFreeでサービスするものは顧客が欲しいと思うものであるか、そのきっかけにするものなのかは様々だ。しかし、FreeはまさにWinWinの関係を作るための仕掛けといえる。
購入サイドから考えると、これからは、何か欲しいものを購入する際にそれだけで買ってはいけないということになる。何かFreeのサービスがついていなければ、損だと考えるべきなのだ。
むしろ、Freeのサービスがついている店を選択し、結果として本来欲しいものを購入するのが賢い消費者といえよう。
購買の立場からも販売の立場からもFreeが今後のキーワードになるだろう。
商品そのものだけを売ろうとしても消費者は買わない。「何かオマケをつけないと他で買うわよ!」
ということだ。
しかし、そのオマケはアトムではなくビッドで提供すると驚くほどFreeに近く提供できるのだ。買う方もサービスがFree。売る方もサービスをFreeで提供できる世界がやってきた。
両者がどのようなFreeのサービスを選択するか。
それは現代の紙芝居。
どのような顧客にどのような紙芝居を見せるか。
紙芝居は販売のキーとなるオマケなのだ。
最近のコメント